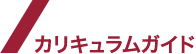「比較学習」「古典重視」「鑑賞教育」の3つに集約されます。「比較学習」は、3領域それぞれの時代的・地域的比較はもとより、領域相互の比較検討、そして他の人文諸学との比較も含まれます。芸術が本来、各ジャンルの相互関連により成り立っていることを前提としたものです。「古典重視」は文字通り東西の古典テクストの読解を重視することです。「鑑賞教育」は生の芸術作品の鑑賞を踏まえた教育です。これら基礎の段階から徐々に専門へと、段階を追ってカリキュラムは設定されますが、大切なことはまず固定観念を棄てること、そして改めて自分にもっとも合った専門領域を選択していくことです。結果としてそれは、学生諸君の以後の幅広い芸術的視野からの学習・研究を可能とし、将来的には社会への着実な貢献を約束してくれるでしょう。
 これまでのゲストスピーカー(年度をクリックすると開きます)
これまでのゲストスピーカー(年度をクリックすると開きます)
2024年度
2023年度
2022年度
2021年度
2020年度
2019年度
2018年度
2017年度
2016年度
2015年度
2014年度
2013年度
2012年度
課外ワークショップの実施
比較芸術学科では、美術館・博物館、あるいは、劇場・ホールに出向いて、美術・音楽・演劇映像のホンモノに触れる機会を設けています。
毎回、鑑賞後には事前に提示された課題に則ったレポートの提出が求められています。鑑賞後のレポート作成は自分が感じたことを言葉にし、他人に伝えるという訓練に直結しています。2024年度に実施予定の催しは以下の通りです。
毎回、鑑賞後には事前に提示された課題に則ったレポートの提出が求められています。鑑賞後のレポート作成は自分が感じたことを言葉にし、他人に伝えるという訓練に直結しています。2024年度に実施予定の催しは以下の通りです。
6月
■日本・東洋の美術作品鑑賞(東京国立博物館)
7月
■歌舞伎鑑賞教室(国立劇場主催公演)
後期
■日本フィルハーモニー交響楽団定期演奏会
芸術鑑賞サロンの開催
芸術鑑賞は、教員から学生へと教えるような縦の関係で成立するものではありません。互いに一体となって作品の素晴らしさに身を委ねる、そんな対等な関係においてこそ、真の鑑賞体験は成り立つものです。原始時代の人々はなんのために芸術を生みだし、なんのためにそれを必要としたのでしょうか。私たちはそのような原点に立って芸術を考え、味わう場として、芸術を鑑賞し合うサロンを開催し、授業ではなかなかすべてを取り上げることが難しい舞台作品や映画を、ビデオなどで全編鑑賞する機会を設けています。これまで、映画や歌舞伎、戯曲、オペラを鑑賞し、教員が適宜解説を加えつつ、その作品についての理解を深める場として、活発な議論が戦わされました。教員が個人的に所有する「本物」の美術作品を、直接鑑賞する機会なども設けられています。

|
芸術を「比較」しながら学ぶ 「比較」による学習・研究は、この学科の学びの基本です。1年次の「比較芸術学入門」は、本学科の専任スタッフと一部非常勤講師によってオムニバス形式でおこなわれるもので、展覧会や演奏会、舞台、映画などの鑑賞を前提に、その解説とレポート作成によって「美術」「音楽」「演劇映像」の実際を比較しながら体験的に学びます。1・2年次の「各領域と文芸」でも、2分野以上を選択することで各領域と文芸との関係とそれぞれの本質を学びます。 |
文章のデッサン力を鍛える この学科では1年次の「比較芸術学入門」から3・4年次の「演習」にいたるまで、生の作品鑑賞を基本とする学習・研究を積み重ねます。そこでの鑑賞レポートはたんなる感想文ではなく、その作品が具体的に美術なら形体や色調、構図その他、音楽なら楽器や声の音色、アンサンブルその他、演劇なら役者の所作やせりふ回しその他等々、細部にいたる観察による言語化(ディスクリプション)の訓練を義務づけ、言葉のデッサン力の獲得を目指します。 |
|
古典テクストを読む 本学科は生の芸術作品を鑑賞することと並行して、古典テクストの読解にも力をいれます。芸術作品はいわば歴史や文化の「非文字資料」ですが、やはりそれらの編年や意味の詳細を理解するには文字資料であるテクストの読解が不可欠です。ある国の美術や音楽、演劇映像を真に理解するには、その国々の言語を理解せずして済ますことはできません。「原書講読」では英語はもちろん、漢文・古文のテクストもとり上げます。 |
芸術鑑賞の基本を学ぶ 「芸術鑑賞の方法」では、そこに何が表され、何を意味しているのかという美術解釈の基本となる図像学をはじめ、具体的な美術作品の調査法、絵画や彫刻の簡単なデッサンの技法、西洋音楽や日本伝統音楽の楽曲分析、古い楽譜の解読や演奏法、日本古典芸能や西洋演劇では演技者や舞踊家による実技を前提とした所作や動きの意味、道具の役割など、作品鑑賞に必須の基礎知識を学びます。 |
| 学科科目(必修) | 学科科目(選択必修) | 外国語科目 | 青山スタンダード科目 | 自由選択科目 | 卒業要件単位 |
| 20単位 | 50単位 | 8単位 | 24単位 | 26単位 | 128単位 |
- 1年次
- 鑑賞教育の基礎を学ぶことにより、Ⅰ美術・Ⅱ音楽・Ⅲ演劇映像それぞれのジャンルの通史的理解を前提に、それと同時代の諸文芸との関連を比較・学習することで芸術系3領域それぞれの特性のより明確な把握を目指す。
- 2年次
- 各領域における「基礎演習」「原書講読」「鑑賞の方法」などの専門科目の比較学習・研究を徹底することにより、各領域それぞれの共通性や異質性への学問的認識を深める。
- 3年次
- 2年次よりひきつづき、比較学習、研究を徹底する。各領域の専任教員のもとで本格的な演習の履修がはじまり、より専門性の高い教育内容の修得を目指す。
- 4年次
- 各領域ゼミナールとも選択必修科目の「特別演習(卒業論文)」により卒業論文(本文2万字程度)の作成指導をおこない、専門的研究の出発点とする。各専門領域の知識のさらなる修得に努める。
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 専門基礎科目 | 比較芸術学入門A/比較芸術学入門B/西洋の文芸と美術A 西洋の文芸と音楽A/西洋の文芸と演劇映像A/ 日本・東洋の文芸と美術A/日本・東洋の文芸と音楽A/ 日本・東洋の文芸と演劇映像A |
芸術と文学/芸術と法 | ※領域は次のように表されます。 Ⅰ 美術/Ⅱ 音楽/Ⅲ 演劇映像 |
||
| 専門選択科目 (イ)~(ホ)までは上記による、2つ以上の領域から単位を取得すること |
(イ) | 西洋の文芸と美術B/西洋の文芸と音楽B/西洋の文芸と演劇映像B/日本・東洋の文芸と美術B/日本・東洋の文芸と音楽B/日本・東洋の文芸と演劇映像B | |||
| (ロ) | 基礎演習 Ⅰ(1)(2)(3)、Ⅱ(1)(2)、Ⅲ(1)(2)(3) | ||||
| (ハ) | 原書講読 Ⅰ(1)(2)(3)、Ⅱ(1)(2)、Ⅲ(1)(2)(3) | ||||
| (ニ) | [芸術鑑賞の方法 Ⅰ ](1)絵画の制作を通した美術作品の鑑賞法 (2)西洋美術作品の鑑賞法と鑑賞発表 (3)国内外の美術館・博物館の成立史と鑑賞法 [芸術鑑賞の方法 Ⅱ ](1)中世・ルネサンス・バロック音楽の記譜法 (2)バロック音楽における修辞学 (3)民族音楽学・音楽人類学からみる世界各地の多様な文化 [芸術鑑賞の方法 Ⅲ ](1)歌舞伎と歌舞伎舞踊の表現や仕組み (2)歌と踊りのない演劇はなぜヨーロッパで生まれたのか (3)映画におけるドキュメンタリーとフィクションについて | ||||
| (ホ) |
[比較芸術学特講 Ⅰ ](1)キリスト教文化における造形イメージのあり方 (2)イメージとマテリアリティ (物質性) (3)西洋美術史学の方法と歴史 (4)近現代彫刻史とその展開 (5)日本文人画と近代の「東洋憧憬」 (6)日本中世近世絵画における「描かれた祭りと名所」 (7)神像彫刻の出現と展開 (8)日本における「異神の図像学」 [比較芸術学特講 Ⅱ ](1)近代フランス音楽の「三大作曲家」フォーレ ・ドビュッシー・ラヴェル (2)義太夫狂言の音楽的な特徴 (3)・(4)チャイコフスキーのオペラ《エヴゲニー・オネーギン》の楽曲分析 (5)リヒャルト・ワーグナー 歌劇『タンホイザー』 『ローエングリン』研究 (6)オペレッタ研究 ヨハン・シュトラウス二世『こうもり』フランツ・レハール『メリー・ウィドウ』 [比較芸術学特講 Ⅲ ](1)フランスの演劇人「ヴァレール・ノヴァリナ」 作品分析 (2)西洋近現代演劇における「祝祭」概念の変遷 (3)・(4)「歌舞伎における悪」 (5)・(6)アメリカと日本の映画通史 |
||||
| (ヘ) | 比較芸術学演習 Ⅰ(1)(2)(3)(4)、Ⅱ(1)(2)、Ⅲ(1)(2)(3) | ||||
| (ト) | 特別演習(卒業論文) | ||||
| 選択科目 | 美学・芸術思想/西洋の宗教と芸術/日本・東洋の宗教と芸術 | ||||
| 博物館実習Ⅰ/博物館実習Ⅱ ※3年次・4年次のみ履修可能 | |||||
| 外国語科目 | 英語講読 Ⅰ/英作文 | 英語講読 Ⅱ/オーラル・イングリッシュ | |||
| 全学共通科目 | 青山スタンダード科目 学部・学科の所属に関わりなく、専門領域を越えて様々な学問分野の知識を身につけます。 | ||||
| 自由選択科目 | 学科科目、青山スタンダード科目、外国語選択科目の必要単位以上の履修、文学部共通科目、文学部他学科、他学部開講科目の履修が可能です。勉強したい科目を自由に選択し、卒業に必要な単位とすることができます。 | ||||